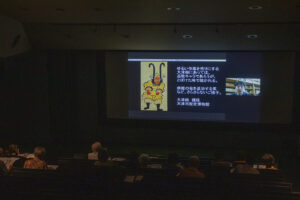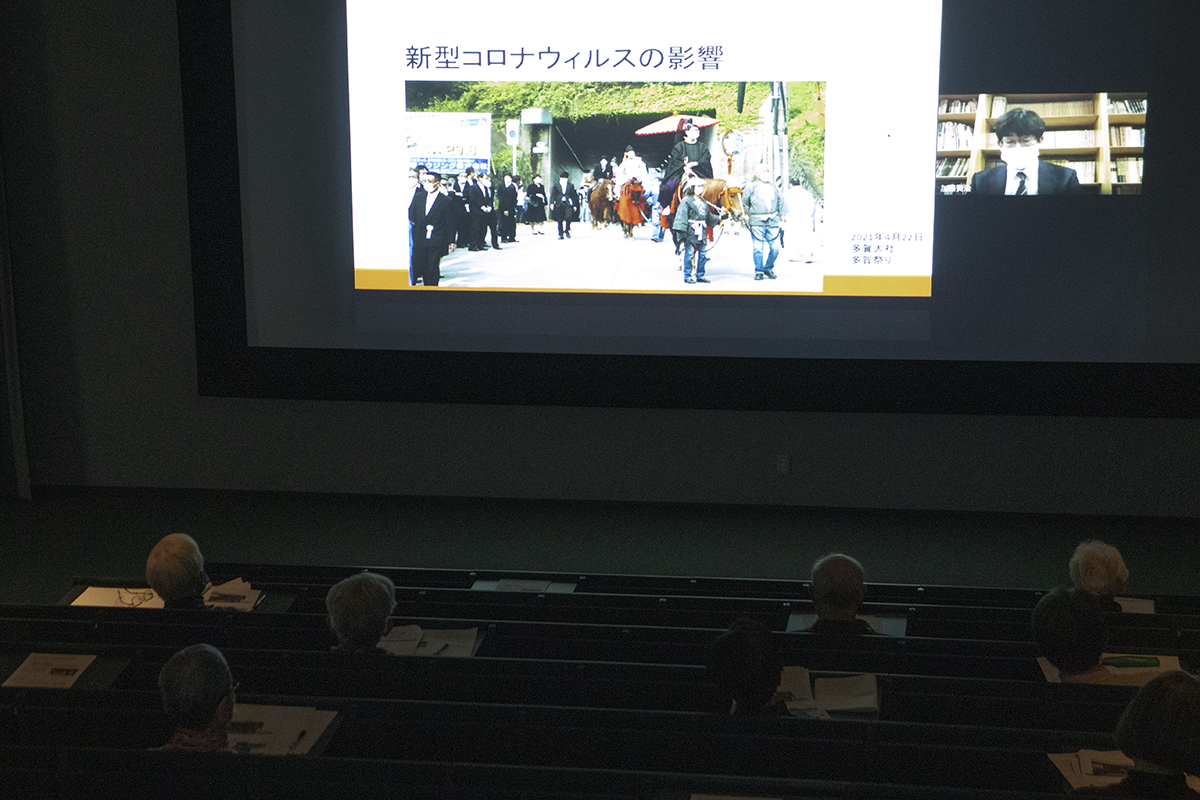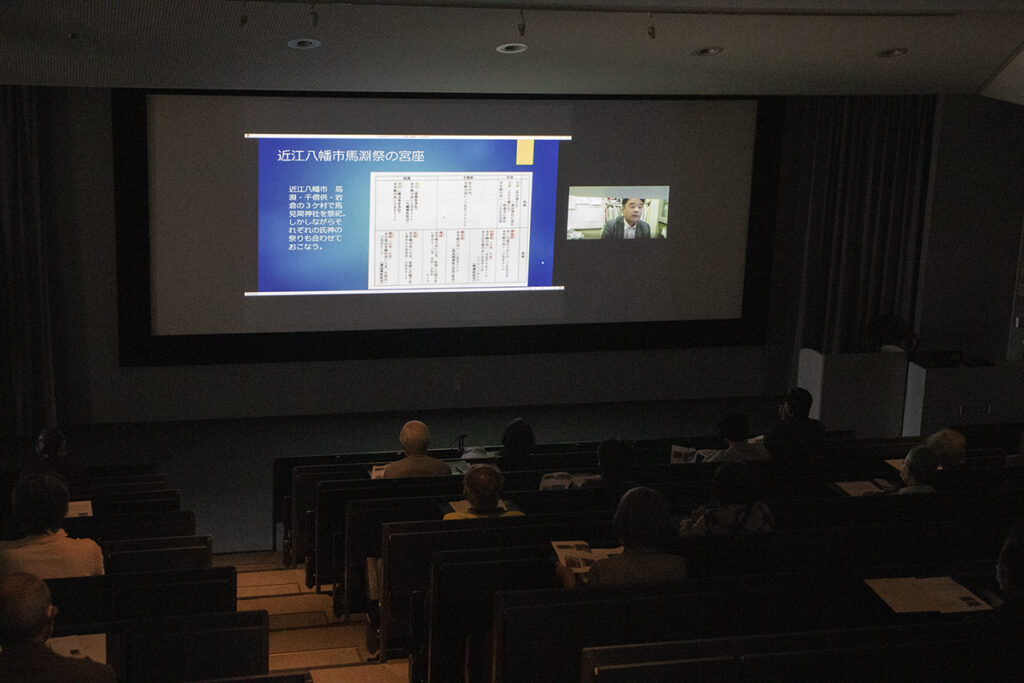近江学フォーラムニュース
第14回近江学フォーラム 現地研修「紫式部ゆかりの古刹 石山寺を歩く」報告

2023年10月28日(土)に、第14回近江学フォーラム 現地研修「紫式部ゆかりの古刹 石山寺を歩く」を開催しました。
昨年度に引き続き、現地集合・現地解散、午前と午後の二部に分けて人数を分散して実施しました。

今回の現地研修には、近江学フォーラム会員のみなさま45名(午前の部23名/午後の部22名)、スタッフ10名が参加。
当日、天気予報では雨が降るかどうか微妙な予報が出ていましたが、午前も午後も傘不要で過ごしやすいお天気となりました。
ご参加いただいたみなさま、ご協力いただいた石山寺のみなさまありがとうございました。
■現地研修のようす


今回の研修では石山寺参事の田中眞一様に境内各所についてご解説いただきました。
東大門からスタートし、比良明神影向石、観音堂、毘沙門堂を経て硅灰石の前へ。


寺名にも由来する雄大な硅灰石の前で記念写真を撮影したのち、
すぐ横の階段をのぼり鐘楼へ、そして多宝塔へと向かいます。


多宝塔では、特別に扉を開けていただき、内部のようすを拝見することができました。
その後、月見亭を経て豊浄殿へと向かい「石山寺と紫式部展」を見学しました。


豊浄殿を出た後は、最も奥にあり神秘的な雰囲気に包まれている八大龍王社へ。


最後に本堂へと向かい、紫式部の間について加藤副所長から解説があったあと、
特別拝観として本堂内陣へと入らせていただき、
鷲尾龍華座主から石山寺についてお話いただきました。
その後、石山寺で俳聖・松尾芭蕉が詠んだ俳句
「石山の石にたばしる霰かな」を表現したお菓子「たばしる」(茶丈藤村)を
みなさんにお配りし研修を終了しました。
(写真:真下武久研究員)
■参加者アンケートより(一部抜粋)
「とても貴重なお話と分かりやすい解説を聞き、参拝しただけでは知り得ない事柄ばかりで楽しかったです。ますます大津の地に愛着が沸きました。」
「天候にも恵まれ有意義な一日でした。御座主からの説明も分かりやすく良かったです。」
「とても興味深いものでした。説明も非常に丁寧で分かりやすかったです。近江学フォーラムならではの、普段は見ることができないところまで見せていただきありがとうございました。
「石山寺を何度も参拝していますが、東大門の淀君の紋や、本堂の菊が裏を向いているなど、普通に参拝しているだけでは気がつかなかったことを知ることができて充実した時間を過ごすことができました。」