おうみブログ
近江学研究所研究員が、近江にまつわるさまざまな情報を発信するブログです。
第15回近江学フォーラム 現地研修「伝説の宝庫 堅田を歩く」報告
2024年10月26日(土)に、第15回近江学フォーラム 現地研修「伝説の宝庫 堅田を歩く」を開催しました。
当日は、現地集合・現地解散、午前と午後の二部に分けて人数を分散して実施しました。

今回の現地研修には、近江学フォーラム会員のみなさま45名(午前の部23名/午後の部22名)、
スタッフ11名が参加。
当日は、天候も良く、過ごしやすいお天気で現地研修日和となりました。
ご参加いただいたみなさま、ご協力いただいたみなさまありがとうございました。
■現地研修のようす
今回の研修では、趣のある堅田の町を歩きながら、
各所でご住職や加藤副所長にご解説いただきました。
受付では、本学の学生がキャラクターデザインを手がけた、
「一休せんべい」と「らくがんさんの落雁」を参加者特典としてお配りしました。
まずは本福寺からスタート。
貴重な宝物を特別に拝観させていただきながら、
三上住職から、思わず聞き入ってしまうような熱のこもったご解説をいただきました。


本福寺を後にし、つづいては浮御堂を拝観しました。
浮御堂は既に訪れたことのある方も多かったですが、加藤副所長の解説もあり、
新たな発見や学びがありました。


続いて伊豆神社にて、研究員との記念写真を撮影後、境内を見学しました。


伊豆神社を出た後は、光徳寺を訪れました。
本堂の前には、蓮如上人の法難に対し、実父を説得し、
自らの首を打たせて差し出させた姿を表す「堅田源兵衛父子殉教之像」があり、
加藤副所長から源兵衛親子の殉教の物語について解説がありました。
その後、本堂に移り、伊藤住職から源兵衛の父が息子の首を打った以後のお話があり、
本堂に安置されている御首級(みしるし)を特別に拝観させていただきました。


次にとんち話で知られる一休宗純が青年時代に修行をしたことで有名な祥瑞寺へ。
残念ながら本堂へは入れませんでしたが、
趣ある庭園や建物を眺めながら加藤副所長からの解説を聞きました。


祥瑞寺のあとは、都久夫須麻神社、十六夜公園、辻家前を見学しながら堅田の町並みを歩き、
最後は天然図画亭を訪れました。
座敷からは、すばらしい庭園の向こうに、琵琶湖と対岸の山並みを見ることができました。
そんな景色を眺めながら、老舗和菓子店「金時堂」の主人、山本伸一さんにお菓子についてや
歴史ある堅田の町並みについてお話しいただきました。


参加者同士のお話にも花が咲いていたのが印象的で、話は尽きない様子でしたが、
盛況のうちに無事研修を終了することができました。
(写真:真下武久研究員)
■参加者アンケートより(一部抜粋)
「とても楽しく勉強になりました。初めての方とも交流できて良かったです。」
「交通の要、堅田の重要な歴史や文化を浮き彫りにしていただいた講座でした。楽しい一日をありがとうございます。」
「なかなか中にまで入れなかったところも入れ、丁寧に説明していただき、今日来れてよかった!」
「深く学べました。先生や住職の話しなど、楽しく散策しました。金時堂のご主人の話もイメージに残るステキなお話しでした。」
「淡海の夢2024 堅田・湖族の郷写生会」を開催しました!

「淡海の夢2024 堅田・湖族の郷写生会」
日時:10月12日(土)9:30~17:00
場所:大津市堅田周辺
講師:永江 弘之(本学イラストレーション領域教授・本研究所研究員)、待井 健一(本学イラストレーション領域准教授)
10月12日(土)、大津市堅田にて、公開講座「淡海の夢2024 堅田・湖族の郷写生会」を開催しました。
「淡海の夢」は、年2回の写生会と公募風景展を通して、近江の素晴らしさを体感し、近江の固有の価値を再発見する講座です。
当日はとても良いお天気で、一般の方30名、学生3名にご参加いただきました。

今回の写生会では、漁港や浮御堂など趣深い堅田の風景を描きました。
まずはじめに講師から写生中の注意点などの説明を受けていただいた後、参加者のみなさんは、それぞれ思い思いの場所で風景を描きます。
講師は、写生中のみなさんを巡回して個別に風景写生のコツについてアドバイスを行いました。


15:30からは、本福寺本堂にて、作品鑑賞会を開催。みなさんの作品がずらりと並びました。
暑い一日だったのでみなさんお疲れの様子でしたが、一般の方も学生たちもお互いの作品を鑑賞しながら、情報交換に花が咲いていました。

受講者のみなさんからは、
「皆さんの作品も、様々な画材や着眼点でとても参考になりました。」
「好天に恵まれ、楽しく描くことができました。先生方のご指導も丁寧で分かりやすく感謝いたします。」
「講師の方々のいつもながらのわかりやすい説明、毎回参考にさせてもらっています。」
「スケッチポイントがたくさんあり何度でも訪れたい町でした。意欲的に取り組めました。」
など、たくさんのご感想をいただきました。
【開催決定】「淡海の夢2024写生会」堅田・湖族の郷写生会
淡海の夢2024 堅田・湖族の郷写生会
お申込みの皆さま
本日(10/12)の写生会は、予定通り開催いたします。
熱中症対策および日かげでの寒さ対策に十分ご留意いただき、
ご参加くださいますようお願い申し上げます。
どうぞお気をつけてお越しください。
成安造形大学附属近江学研究所 10月12日(土)7:15
近江学フォーラム会員限定講座「旧瑞峯院方丈襖絵「 堅田図」にみる中世堅田の暮らし」報告
令和6年度 第3回 近江学フォーラム会員限定講座
「旧瑞峯院方丈襖絵「 堅田図」にみる中世堅田の暮らし」
【会員限定講座】
日時:9月28日(土)11:00~12:30
場所:成安造形大学 聚英ホール
講師:和田光生 氏|元大津市歴史博物館副館長・大谷大学非常勤講師

令和6(2024)年度第3回目の近江学フォーラム会員限定講座を開催しました。
今回の会員限定講座では、16世紀半ばに描かれた旧瑞峯院方丈襖絵「 堅田図」について、元大津市歴史博物館副館長で本研究所の客員研究員でもある和田光生氏に絵解きしていただき、当時の生業や人々の生活についてご講演いただきました。

講座のはじめには、本講演のテーマである「 堅田図」について、文化誌「近江学」第15号で日本美術史の観点から考察を行った小嵜善通教授(本学学長・本研究所所長)からもお話をいただきました。

「堅田図」には、地形をはじめ、家屋や船の形、漁具や漁法、農具や農業など、当時の人々の暮らしぶりが細部まで描かれています。今回の会員限定講座では、その一つひとつについて丁寧に読み解き、そこから当時の人々がどのように暮らしていたのか、またどういった生業を営んでいたのか、現在の町の様子とも比較しながら、和田先生の考察をお話いただきました。
受講者のみなさんからは、
・古地図を現地図と重ねて見る事が好きなので大変よかった。絵から現在の地形を読み解くのが面白かったです。
・堅田という町、湖族のこと、成立ち、地形、水路等いろいろ詳しく聞かせていただき住民として誇りに思いました。
・中世の生活の様子、町の形成など、具体的に説明されて当時の様子が理解できた。堅田の町の特徴がよく描かれていて感心した。
・その当時の人達の生活の様子が知れてとても興味深く面白かったです。ぜひ実物が見たくなりました。
などといったご感想をいただきました。
[講師プロフィール]
和田光生氏 (元大津市歴史博物館副館長・大谷大学非常勤講師)
1960年、滋賀県生まれ。佛教大学大学院文学研究科日本史学専攻修士課程修了。
大津市歴史博物館副館長を経て、現在、大谷大学非常勤講師。
主に近江の社寺に関する歴史民俗学的研究を行う。
研究発表では『近江地方史研究』28号、共著に『高月町史 景観・文化財編』などがある。
<誤植のお詫び・訂正のお知らせ>
近江学フォーラムの会報誌で、フォーラム会員及び文化施設等にも配布しております近江通信紙Vol.31内の表記に誤りがございました。
深くお詫び申し上げますとともに,下記の通り訂正させていただきます。
●該当箇所:2⾴、「3拠点生活のすゝめ 」の執筆者名
【誤】三宅 正治
↓
【正】三宅 正浩
近江学フォーラム会員限定講座「惣-私たちの公」報告
令和6年度 第2回 近江学フォーラム会員限定講座
「惣-私たちの公」
【会員限定講座】
日時:7月27日(土)11:00~12:30
場所:成安造形大学 聚英ホール
講師:水本邦彦 氏|歴史学者・京都府立大学名誉教授

令和6(2024)年度第2回目の近江学フォーラム会員限定講座を開催しました。
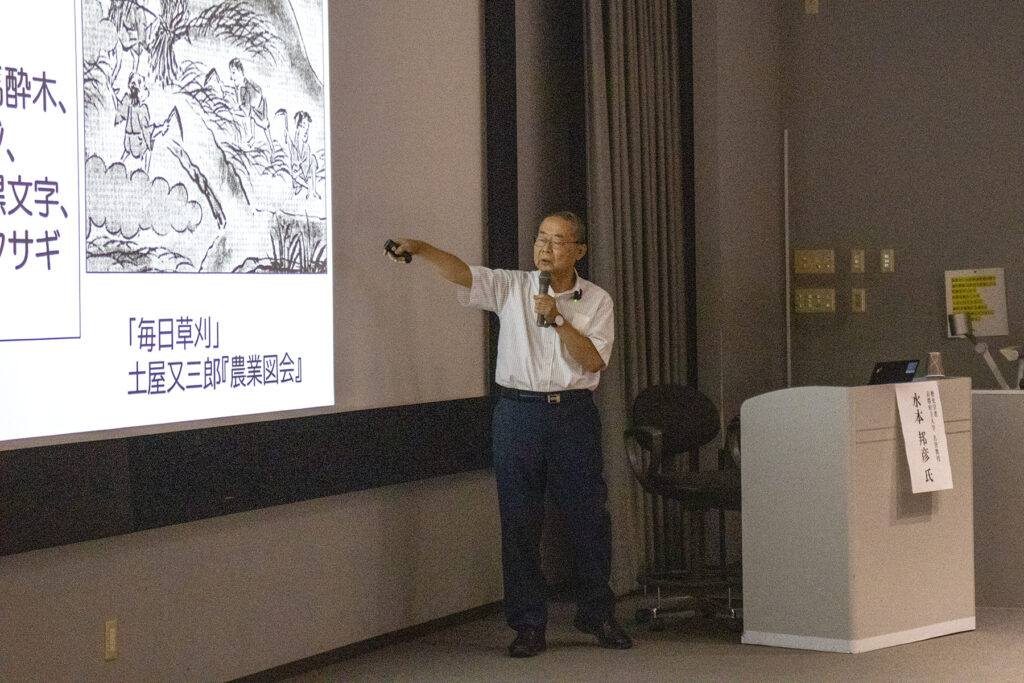
今回の会員限定講座では、日本において、14世紀ごろから19世紀後半に作られた「惣」というコミュニティに存在した
独自の「掟」、いわゆる「公(おおやけ)」について歴史学者であり、京都府立大学名誉教授の水本邦彦氏にご講演いただきました。
「私たちによる、私たちのための、そして私たちを縛る」いわゆる「公」というものは、村人が自ら作ったゆるぎない掟として
絶対的な力を持っていたと解釈されています。
水本先生には、実際に今に伝わる古文書をもとに、掟でつながる江戸の村社会の姿を紐解いていただきました。
受講者のみなさんからは、
・身近な地域の掟などの歴史を知ることができて面白かった。
・草肥農業から金肥農業への変化の話が面白かった。
・江戸時代の「惣」の維持管理の状況がよく分かりました。
かなり厳しい掟を決め、惣を維持しており、惣の自治を守っていたことがうかがえました。
・日本の村の生い立ち、村の縛りの原点がよく分かる講義であった。
などといったご感想をいただきました。
[講師プロフィール]
水本邦彦氏(歴史学者・京都府立大学名誉教授)
1946年、群馬県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。文学博士。京都府立大学名誉教授・長浜バイオ大学名誉教授。
専攻は日本近世史。古文書に加えて、絵図や屏風絵などを活用しながら、日本近世という時空間の構造的・写実的な描写をめざしている。
主な著書に『近世の村社会と国家』(東京大学出版会)、『徳川の国家デザイン』(小学館)、『草山の語る近世』(山川出版社)、『村 百姓たちの近世』(岩波新書)などがある。

