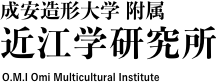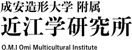仕事納めを終えた平成21年最後の日曜日、師走27日に湖北菅浦を訪ねました。近江を愛した随筆家白洲正子がその著書『かくれ里』でとりあげた集落です。大学から湖西路を北にゆっくり走って約2時間、今津をこえ、桜で有名な海津方面へ湖岸を行く。有名な桜の木々はこの時期全くの冬枯れでした。ただ、この日は普段なら身に染みる寒さと時雨模様であるはずですが、天候に恵まれおだやかに晴れており過ごしやすい一日でした。
菅浦はかつて陸の孤島と呼ばれ、湖上からでないと集落に入ることが出来ませんでしたが、地理上のこの立地が村に様々な伝承を伝えています。村の東西の入り口には草葺の棟門(四足門)が中世村落の雰囲気を伝えてくれます。その東の門を入ったところにこの村の中心となる須賀神社があります。この神社の祭神は淳仁天皇(733~765)で、村の人々はこの淳仁天皇に仕えた人々の子孫であると言い伝えられています。淳仁天皇は奈良時代の末期、孝謙上皇や弓削の道鏡、藤原仲麻呂らの政争に巻き込まれ、淡路に流され非業の死を遂げた廃帝として知られますが、菅浦には淡路というのは淡海(近江)の誤りで、そのなきがらを菅浦の人々がこの地に葬ったという伝説があります。
白洲正子の『かくれ里』にはその伝承が詳しくつづられています。須賀神社に参拝されたシーンで
「神社の石段の下で、私たちは靴をぬがされた。跣(はだし)でお参りするのがしきたりだそうで、たださえ冷たい石の触感は、折りしも降りだした時雨にぬれて、身のひきしまる思いがする。それはそのまま村人たちの信仰の強さとして、私の肌にじかに伝わった。」という一節があります。今でも石段の下には「土足厳禁」という石版がありましたが、白子氏が参拝されたときと違いその石版の下にスリッパが置いてありました。
そのスリッパをお借りして参拝を済ませ、石段を降りる途中、奥琵琶湖の深い青色の湖面に日の光がきらめき、古い瓦屋根の集落を眺めていると、タイムスリップをしたような非日常を心身ともに深く感じました。
加藤賢治(近江学研究所研究員)

四足門

須賀神社

菅浦